こんにちは。ゆみずです。
みなさん。
心理機能というものはご存知ですか?
心理機能を簡単に言うと、人間の情報処理の仕方です。
全部で8つあります。
人間の成長とは、この8つの心理機能をバランス良く成長させていくことであると思っています。
今回は、8つの心理機能の1つ、内向的思考Tiをご紹介しましょう。
書籍などの知識や私の経験をわかりやすくまとめました。
内向的思考を鍛えることは、言語化能力UPにつながったりします。
また、内向的思考を使うことが多いタイプ(INTP、ISTP、ENTP、ESTP)が、どのように普段考えているのかを詳しく知ることができます。
これらのタイプが何を考えているか知りたい人はぜひ読んでください。
内向的思考(心理機能Ti)とは、独自理論をつくる能力

内向的思考(Ti)とは物事に論理と一貫性を求める能力のことです。思考の方向が、自分の内側へと向かっていきます。外部の意見や常識に頼るのではなく、「自分が納得するかどうか」を重視します。そのため、自分独自の理論をつくることができます。
また、理屈や意味を抽象的・観念的なものに結びつけます。例えば、「人はなぜ生きるのか」「真実とは何か」「善悪とは何か」など物事の原理原則・本質について興味を持ちます。
理論の整合性を求め、内面的な世界に溺れていく感覚が好きなのです。
その他特徴は下記です。
- 個人の自律性や独立性、自由を求める。(自分を自分でコントロールしたい欲求)
- 深い論理に基づいて、問題を解決しようとする。
- 深い懐疑心を持つ
- 暗黙の論理で動く(みんなにはわからない論理)
- 主観的で自由な論理
- 独自の理論、方法をつくる
- 左脳的かつ右脳的
- 即興的
- 柔軟性あり(目の前の状況に合わせて行動)
- 本質を追求(なぜか?を問う)
- 論理の矛盾を簡単に特定(真実であるかないかを簡単に特定)
- 自分と他者(外部環境)の課題を区別して、線を引く。
- 目測という手法を使う
- 視覚データと運動感覚データを統合させる
【具体例】内向的思考(心理機能Ti)の使い方

 INTPロボ
INTPロボなんとなくわかったけど、少しむずかしいよ。



それでは、Tiが得意な人の具体例を上げてみよう。
例えば、上司から仕事を振られました。
内向的思考(Ti)が得意な人は、まず自分で考えます。
「この仕事の目的はなんだろうか。」「この仕事の背景はどのようになっているのか。」
自分で考えましたが、わかりません。
これらを上司に質問しました。
しかし、上司の返答を理解できませんでした。自分の頭では納得できません。
そこで、紙に書き出し、それを自分なりに理解しようとします。
集めた情報から自分なりのロジックを組んだり、過去の経験や知識とつなげたり、新しい情報を求めて他の人に聞いたりネットで調べて理解しようとします。
すると、独自の論理を作り上げることができ、自分なりの納得感を生み出すことができました。
やっと仕事の実行へと移ろうとします。
Tiとは、社会的地位の高い人が言ったから納得したというのではなく、自分のなかで納得いく論理が組めたかという基準で納得します。別の言い方をすれば、他人の意見や権威に左右されず、独自の論理やアイデアを構築できるということです。
【内向的思考(心理機能Ti)】4つのメリット
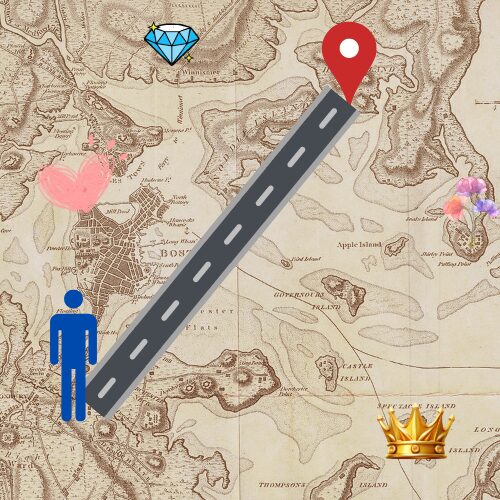
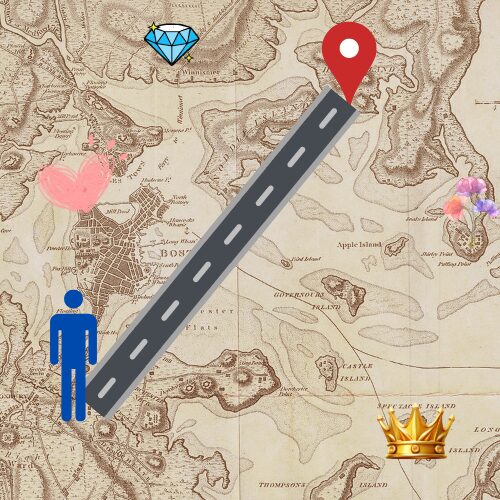
①自分なりの幸せを定義できる
Tiは内省を好みます。自分のことなどを理解しようと、言語化する能力です。
例えば、
- 自分はなんのために生きているのだろうか?
- 自分の本当にやりたいことってなんだろう?
- 自分の得意なことはなんだろうか?
これらを理屈で説明しようとすることが多いです
そのため、Tiがうまく使えている人は、自分についてよく知っている人が多い印象です。
自分が何に充実感を覚え、何に時間の無駄を感じるのかをよく理解しています。
だから、Tiが得意な人は、まわりの人とは異なる自分だけの幸せを言葉にして定義することが得意なのです。
②人に騙されにくいかも
Tiは、自分の中のロジックで物事を理解するため、外部からの情報を鵜呑みにしにくいです。
例えば、「この14万円のインソールを履けば、肩こりが治ります。買いませんか?」と言われたとします。
内向的思考が得意な人は、
- このインソールでなぜ肩こりが治るのか?どういう理屈なのか?
- 肩こりの原因とは、何が一般的なのか?
- 肩こりを治すために、インソールを買うことは一般的な問題解決のアプローチなのか?
- 普通のインソールを履いている人には、肩こりがひどいのか?
- なぜこのインソールは14万円もするのか?
- この販売員の目的は、高額なインソールを販売して大きな利益を得ることが目的ではないのか?
などの疑問がわきます。
③本質をとらえた問題解決ができる
Tiは、複雑な問題に対して本質を見抜くことが得意です。
なぜなら、「なぜを問う力」が優れているからです。情報やデータを集めて、それらの因果関係を構造的に整理して、全体を体系的に理解します。
だから、複雑な問題に対して、本質(どの問を解くことが効果的か)がわかるのです。
④創意工夫して楽しめる
内向的思考が得意な人は、創意工夫して独自の理論や方法をつくることが得意です。
これは、物事を理解するときに、独自の方法や推論を好むからです。ただ、外部から決められた方法が合理的であれば喜んで使いますが、非合理的・感情的であれば抵抗感があります。
現実世界で有効な独自の理論や方法をつくるためには、直観(本質・可能性を捉える力)と感覚(実際の体験・具体的事実を捉える力)の両立が欠かせません。
別の言い方をすれば、「本などから得る理論や知識(二次情報)」と「自分の体験や観察を通じて得る現実的な知恵(一次情報)」の両方をバランスよく取り入れることで、抽象と現実がつながり、より効果的で実践的な問題解決が可能になります。
【内向的思考(心理機能Ti)が過剰な場合】気をつける5つのこと


①意思決定の遅れ:考えすぎて行動が遅くなる
Ti過剰な人は、自分の中で納得がいく理解の仕方や理論・方法をつくることに夢中になりすぎてしまいます。時間をわすれてしまい、考えることに時間をかけすぎることがあります。
だから、実行する時間が確保できないことも多いです。



仕事では、致命傷じゃないですか、、、



うん。だから、考える時間を決めることが大切だよ。自分の決めた時間以内に自分が納得できないときは、ゲームオーバーと割り切ろう。
ゲームオーバーなときは、従来の手法や確立されている手法、他人に言われたことをそのまま実行するほうがよいでしょう。実行している中で、また違ったことが見えてきて、自分なりに理解できることも多いです。
②社会性の低下:内面に集中しすぎて、対人関係がおろそかになる可能性
Tiが得意な人は、孤独耐性が高いです。むしろ、孤独になることを1人時間の確保と考えたりしています。Tiは、1人時間を使って、新しくおもしろい概念や理論、方法を1人で創造することができます。
Tiは孤独を消費して、理屈を創造するのです。
そのため、Tiが過剰な人は、人と関わるよりも1人で過ごすほうが有意義と感じて、人と関わらなくなることも多いです。
しかし、人と関わるなかで、新しいことや大切なことを発見することも多いです。人と関わるバランス感覚を大切にしましょう。
③現実との乖離:理想や理論に傾倒しすぎて、現実世界との接点を失うことも
Tiが過剰になると、自分の中で、理論や方法をこねこねすることに必死になってしまいます。だから、その理論や方法が地に足つかなくなることも多いです。



現実感がないのかな?



そうかもしれないな、、だから、現実世界からの一次情報を大切にしてみよう。
できれば、自分の五感を使って、体験・経験してみるのが良いでしょう。そういった一次情報が、地に足ついた理論や方法の創作に役立ちます。
④ストレスの増加:深く考えすぎても、わからないことはわからない
情報が複雑すぎた場合、自分なり理解して納得できないことに苦しむことがあります。自分で情報を整理できたらいいのですが、うまくいかないことも多いです。
そんなときは、新しい知識を入れてみましょう。本を読んだりネット検索したり、人に聞いて情報収集してみましょう。それが、複雑な情報を理解できるヒントになっていくでしょう。
⑤コミュニケーションが苦手:自分の複雑な思考を他人に伝えるのが難しいことも
独自の理論や方法は、人になんとなく説明しても理解されにくいことが多いです。



人から理解されないと、自分がこうしたいなどがあったときに、他人をうまく巻き込めないよね、、



そうそう。だから、自分の理論や方法を、他人にわかりやすく伝える力が必要なんだ。
練習場所は、ブログやSNSがおすすめです。他人が読んでも、理解しやすく・面白く・役立つように書いてみましょう。相手目線で感じて考える練習になります。
内向的思考(心理機能Ti)の鍛え方
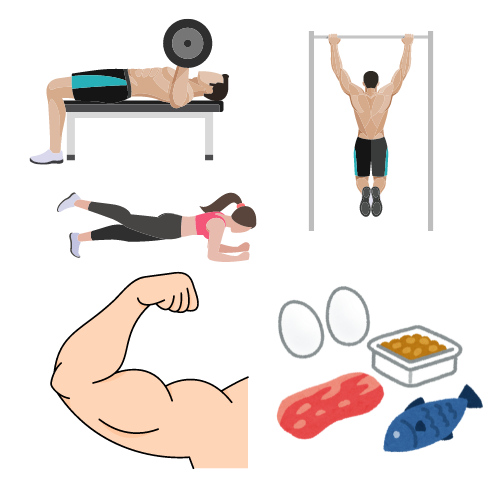
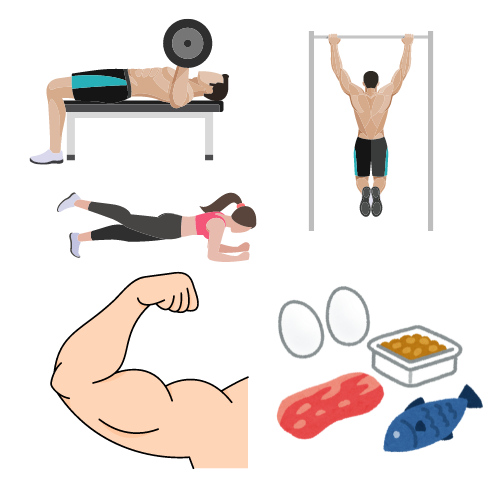
①読書:思考の幅を広げる
いろんな本を読むことで、いろんな知識に触れ、思考の幅を広げることができます。ただ知識を吸収するだけでなく、なにか目的を持って本を読むことをおすすめします。
例えば、人間関係でうまくいかないことがあったとします。この原因の1つに相手への理解が足りなかったと仮定するとします。相手を理解する目的で、MBTIの本を読むのです。そうすれば一冊の本から学ぶことは多くなるでしょう。
②ジャーナリング:自分の思考をノートに書き出し、整理する
日記やジャーナリングをすると、TIが鍛えれます。「なぜ?」を考えたり、自分の思考を構造化・分析する習慣が身につくからです。
実際にやってみると、頭の中だけでは整理できていない情報がたくさんあることに気づくと思います。
インプットするだけでなく、アウトプットしましょう。自分のなかにあるイメージや感覚を言葉にする練習をしてみましょう。
ただ感情を吐き出しているのは、Fi(内向的感情)に近いです。そのため、理屈っぽく書いてみると、Tiが育っていきます。「ここから、なにが学べたのか?」を考えていくこともおすすめです。
③一人の時間の確保:静かに考えを巡らせる時間を意識的に作る
孤独は、自分のことを深く理解する上で大切です。孤独から、新しい発見が生まれる事も多いです。



他人との会話の中でも、自分のことを深く理解できるのでは?



そうかもな。ただ、その発見を熟成させて、体系立てたり、実際に使えるようにするようには、1人でじっくり考えることも必要なんだ。
孤独を楽しむ内向的思考(心理機能Ti)を周りの人と共有して楽しもう


内向的思考は、独立的・自律的・創造的で自由な思考です。孤独を消費して、1人で思考するあそびを楽しめるでしょう。
しかし、孤立を極めてしまうと、面白くない外部環境を自分で作ってしまう可能性があります。
より人生を充実させるには、自分が考えた面白い思考を聞いてもらう仲間がいるほうがいいのではないでしょうか。案外、仲間とワイワイするのも楽しいものです。
では、また。



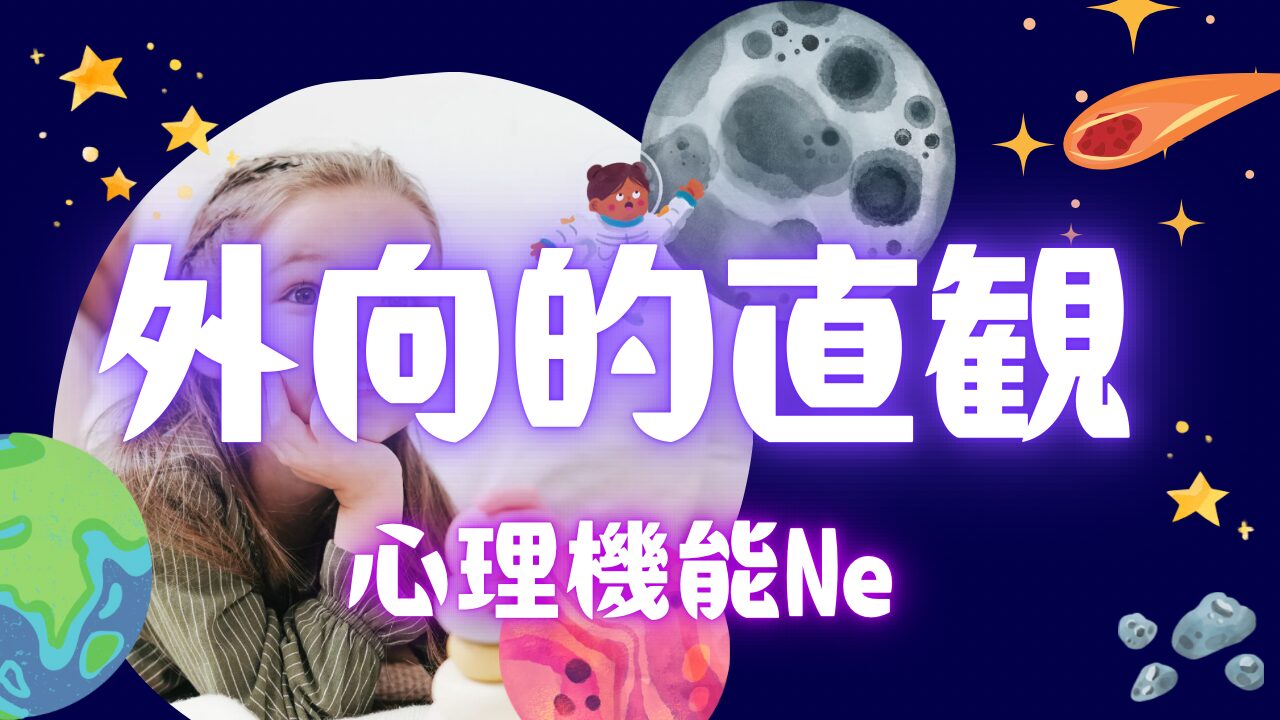



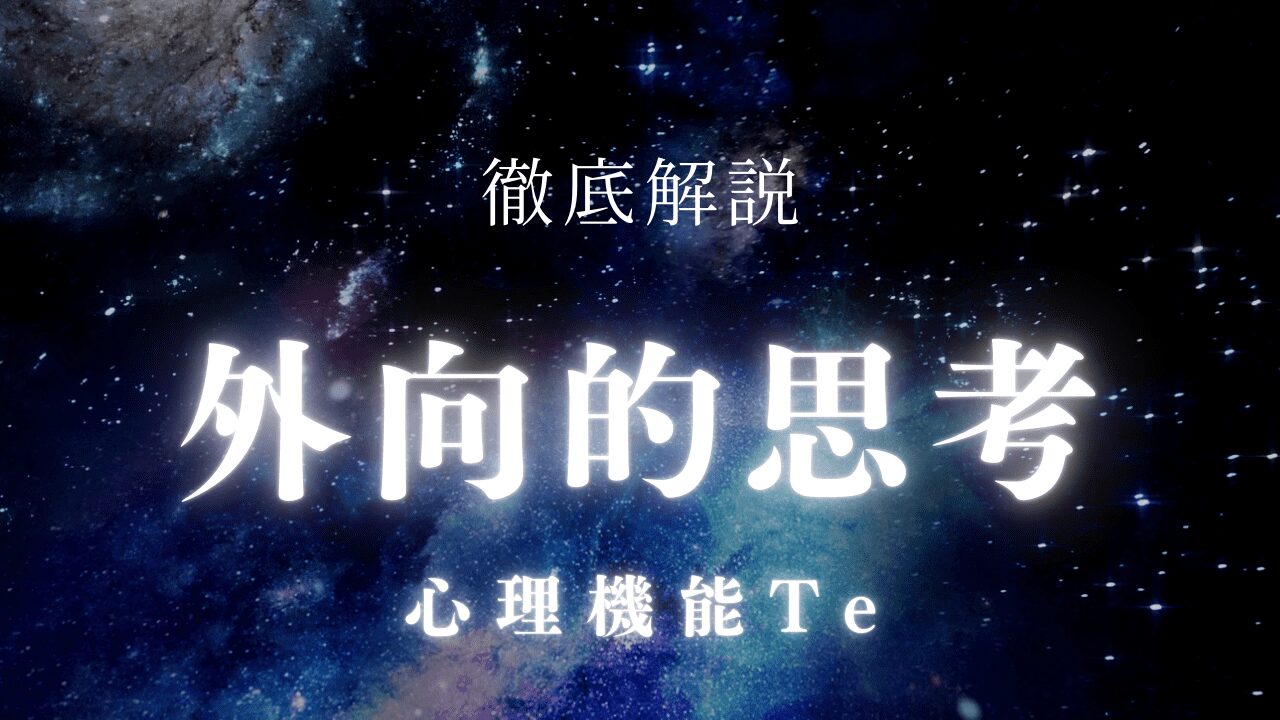





コメント